| イチゴの新品種「章姫」 |
|
■萩原先生の栽培ポイント <章姫の栽培(基本)> 1.章姫の大果多収のために いままで永い間、花芽分化のことや、受粉、受精のことが強調されてきたので、その事はそれなりに理解され、実際栽培に応用されてきたことが多くあります。 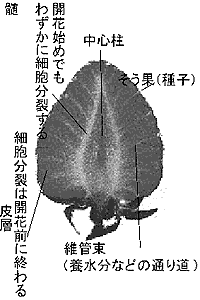 ところが花芽(花房)分化後の花芽の発育段階や、その過程のことについてはあまり提唱されていません。章姫のように大果系のイチゴを多収するには、是非知っておくと都合が良い訳です。 つまり花芽分化後、およそ開花の直前まで細胞分裂が行われながら、花器が完成されていくわけです。とても永い時間がかかるわけです。とくに花托(花床)上につく「そう果(種子)」が、花床の基部から頂部にかけてつくられていくこの過程には時間を要しますし、さらに果実の皮層の部分の細胞分裂も開花直前まで行われています。 大果系のイチゴは「そう果(種子)」の数が多いので、それだけ時間がかかるわけです。だから養水分や光、温度などの条件を、継続して都合よく整えてやることが必要です。 もし根傷みなどによる養水分の過不足が生じますと、発育段階のおそい先端部の「そう果(種子)」に支障が現れます。ひどい場合は、「先づまり果(先しぼみ果)」などといわれる果実を生じます。 イチゴは頂花房の花芽分化に続いて、およそ一ヶ月おきに第1次、第2次、第3次腋花房へと花芽分化が進みます。一方花芽分化したものが、正常な花として花器完成されるまで、およそ4週間余かかりますから、絶えず大切な時期におかれているわけです。こうした連続的な経過は、定植後年末から年明けまで続きます。だからイチゴづくりでは、いまの管理や条件が、1ヶ月〜1ヶ月半先に現れるというわけです。頂花房から数えると4番花房にあたる第3次腋花房までが、年末から年明けまでに花芽分化するわけです。 ところが3番花房といわれる第2次腋花房までは、比較的順調に連続出蕾してきますが、第3次腋花房が、ひどくおくれて中休みしてしまうことが少なくありません。第3次腋花房の発育が足踏み状態にあるわけです。それには複雑な要因があると見られますが、主なことは光合成産物が充分でないことが上げられます。例えば根張りが充分でない、着果過多による光合成産物の競合、光や温度の不足、養水分の過不足、等があげられます。 萩原 貞夫
|
次へ |